
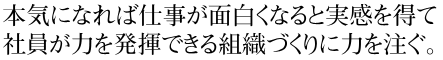


古文書や古典籍などの商いを始めた祖父。それを助け、貧しさの中で苦労を重ねた父は、休みもなく働いて数々の危機を乗り切り、古美術全般に手を広げると、それまでの個人商店を、従業員数十名の会社にまで育て上げた。母に「お父さんはすごい人なのよ」と聞かされても、家では疲れ切って眠るだけの父と言葉を交わすこともなく、ただただ近寄り難い、雲の上の人のように感じていた。
母には「あなたが会社を継ぐのよ」と教えられ、年の離れた姉たちに囲まれて溺愛される一方、外に出れば仲間の先頭に立って山へ川へと飛び回る。学級委員を引き受けても友達と一緒になって女の子をからかい、あっという間に交代させられてしまった。
中学時代には夜遊びを覚え、音楽にはまる。滑り止めに受験した高校に落ちて初めて真剣に勉強し、何とか受かった高校もサボり続けていた2年生の時、父に留学を勧められた。
単身オーストラリアの田舎町に渡り、言葉も通じない中でこの上ない心細さを味わった。日本といえば「フジヤマ」や「ゲイシャ」くらいしか知られていないことに驚きながら、「頼れるのは自分だけ」と進んで交流を深めると、たった3ヵ月で英語をマスターし、現地の友人とバンドを組んでパーティーで演奏するまでになった。
帰国しても真面目に勉強する気にはなれない。それでも父の勧める大学へ進学したのは、「あと4年は遊びたい」という理由からだった。「会社に入ったら、親父みたいに必死で働こう」と思いつつも、大阪や東京の友人宅を転々と遊び歩いて留年した。
4年生になると、バブル景気に乗って美術品が飛ぶように売れ始め、アルバイトに駆り出される。ニューヨークでオークションの通訳を務め、「海外でもこんなもんが売れるんや。俺ならフェラーリ買うのになあ」と、信じられない思いでいっぱいだった。
やがて、かつての級友たちが社会人になっても「俺はまだ仕事せんでええ。ラッキーや」としか感じなかった。しかし、2度目の留年が決まって父に「働きながら単位を取れ」と一喝されると、観念して思文閣に入社した。24歳の時だった。

「思文閣を世界一に」と宣言した歓迎会。何も分からないながら、「頑張りたい」という思いは本物だった。

入社早々5000万円の日本画を目にし、興味は持てないながらも商売の奥深さを垣間見る。「得意の英語を生かして、父にできないことをやりたい」と、入社歓迎会で「僕が思文閣を世界一にします!」とぶち上げて失笑を買った。
1点モノの取引ばかりのため、マニュアル化の不可能な世界。ただ父の言いつけ通りに納品に走り、得意先の講釈を聞いて初めて商品の価値や背景を知る日々。共催の美術展で仲良くなった百貨店の外商担当と、商品のアピールのために資産家の家を回る中で「営業」を教わった。一人前になれば商売の全てを仕切れる代わりに、入社3〜4年は責任ある仕事は何一つ任せてもらえない。焼鳥屋で同僚たちと飲み、「やってられへんなあ」と愚痴をこぼしたこともあった。
同時に、父と一緒に働くほどに、その仕事への情熱を目の当たりにした。小さな個人商店から、出版業、美術館、支店展開と次々に事業を拡大した商才や、業者間で商品を売買する交換会の場で一目置かれる様子に、「やっぱり親父にはかなわない」と圧倒された。
しかし、バブル崩壊を機に商品の評価額は暴落し、売り上げも目に見えて減っていく。そんなある日、美術業界に一斉に国税局の査察が入る。伝票も棚卸しもない昔ながらの商売の不備を指摘され、億単位の追徴課税の支払いを余儀なくされた。
更に、十数億円を投じた新社屋の建設も重なり、資金が底をついて仕入れすらできない。「売るものがなければ会社が潰れてしまう」と不安が募る中、父を師と仰ぐベテラン社員たちが一丸となって「とにかく手元にある商品を売るんや」と、毎晩遅くまで走り回ってくれた。
彼らに感謝しつつも、「商売のことはわかるが、会社のことは人に任せていた」としか言えない父に経営者としての脆さを感じた。顧客からの非難や、美術館との取引停止に直面し、交換会にも行けずに意気消沈する父を見て、「俺は会社づくりに取り組もう。経営者としてなら親父を越えられる」と自分の進む道を見出した。

銀行からの借入れで、何とか危機を乗り切った1993年に結婚し、常務に就任した。しかし、売上減少に対する手立てがないままだった1995年のある日、突然父が倒れた。出張先で緊急手術の知らせを受け、京都へ車を飛ばしながら「親父が死んだら会社はどうなるんや」と、言いようのない恐怖がよぎる。その時の自分にはまだ、会社を背負う自信はなかった。
それでも、社員たちの前に立つと「不安を広げないためにも、俺がしっかりせんとあかん」と自分に言い聞かせた。やがて父の容態は安定したが、完全に仕事に復帰するまでに1年を要した。父に代わって指示を出しながら、社員たちが敬語の使い分けすらまともにできないことに初めて気づき、声を荒げることもあった。それまで全くの放任主義で、基本的な社員教育すらして来なかったという現実に愕然とした。
更に、それまで父に任せ切りだった仕入れも自ら行った。初めて参加した交換会のセリでは、緊張のあまり声が出ない。「ボンボンさん出てきはったで」という周囲の視線が痛かった。必死で勉強し、商品を買い付けるたびに父の病室に駆け込み、「ええもん買うたな」と褒められると、ほっと胸をなでおろす毎日だった。
駆け引きを知らずに高値で買い付け、価値のない作品に1500万円をつぎ込んでしまったこともあった。それでも仕入れの全責任を負い、猛烈な集中力を持続させて、次第に父が不得手だった近代日本画の交換会にも足を運ぶようになった。ある時、今まで見過ごしていた作品の強烈な輝きに初めてハッと胸を打たれ、とっさに「4000万円!」と叫んでいた。
「こんな高いもん、どこに売るんや!」。数百万単位の仕入れを主にしていた父に怒鳴られても、素晴らしい作品であるという確信があった。やがてその日本画は、ある企業が運営する美術館に高値で売れ、「なんて面白い仕事なんや!」と胸が高鳴った。同時に、新しい顧客層の開拓につながる仕入れができたことに喜びを感じ、日本文化の奥深さに魅せられながら、確実に自信をつけていった。