
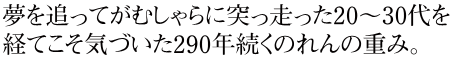

戦後、230年の歴史を持つ料亭を畑の真ん中で細々と再開した祖父が、小学3年生の時に他界した。「新しい日本を引っ張ろう」と現経済産業省に勤めていた父は「のれんを守りたい」という祖母の願いを聞き入れ、できたばかりの阪神百貨店に転職して料亭経営との2足のわらじを履く。「これからはアメリカの資本主義こそ見本だ」といつも語る父の言葉に、まだ見ぬ大国に憧れを持った。
一方で、料亭は来店客のない日が続いて借金が重なり、「店を売ってしまいたい」と漏らす父。住み込みの従業員と沈んだ雰囲気で夕食をとりながら子ども心に商売の大変さを感じ、来店を示す「ごあんな〜い」の声を待ちわびた。
そんな小学6年生の時、阪神百貨店の集客の目玉として父が打ち出した「のれん街」に美濃吉出店の話が持ち上がった。「老舗ののれんが泣きます」と大反対の祖母と業界からの猛反発を押し切り、更に借金を重ねて出店した1958年、開店と同時にのれん街は大ブレーク。中学生になり、夏休みに毎日店を手伝いながら、「これが新時代の小売・サービス業か」とワクワクした。
テレビドラマや映画から垣間見るアメリカにますます夢をふくらませる高校時代。父は事業家としての手腕を発揮して他の百貨店へも出店し、夜は祇園に通って、たびたび息子を呼び出しては派手に遊ぶ姿を見せつけた。そんなある日、父から改まって仏間に呼ばれて、「ゴルフを始めろ」「英語を学べ」「青年会議所に入れ」と言われた。将来の進路については一切語らなかった父の助言を素直に受け入れ、「自分も将来は資本家を目指したい」と思い描いた。

アメリカ政治学を専攻し、ゴルフと英語の勉強に明け暮れた大学時代。父は売上の5倍もの借入れをして本店を料亭から大衆向けロードサイド型レストランに変えることを決めた。土地の半分を駐車場にした新しい店の設計図を見せながら「わしが死んだらお前が借金を返すんやぞ」と冗談交じりに言う父。その言葉に、美濃吉の跡継ぎに生まれた自分の宿命を知って、覚悟を決めた。
「民芸お食事処 美濃吉」へ生まれ変わった本店の開店初日、「こんな辺ぴなところにお客さんが来るんかいな」と心配になって駐車場整理を手伝った。ところがマイカーや観光バスが次々と訪れ、夕方に食材がなくなるほどの大盛況。売上は予測の5倍を記録した。更に、気軽に味わえる京料理として企画された弁当が女性誌で紹介され、あっという間に全国に大ブームを巻き起こした。
そんな中で父と行ったアメリカ外食産業の視察ツアー。そこで、完全にマニュアル管理された1000店規模のレストランチェーンに度肝を抜かれた。「次は外食チェーンで上場するんや!」と、父との間に共通の大きな夢が生まれた。
卒業後、父の期待を背負い憧れのアメリカの大学に留学。3年間夢中になってレストラン経営を学び、28歳で帰国するとすぐに近畿一円を駆け回って、たった2年で25店もの惣菜店を出店。そして31歳の時、神戸の親戚と資本を出し合い、ついに念願の洋食ファミリーレストランチェーン12店の開店にこぎ着けた。
ところが、セントラルキッチンの導入も見据え黒字化に向けスタートを切った2年目、株の8割を握るその親戚と仲たがいし、その結果経営陣から追放された。美濃吉が育てた100名のスタッフの半数は、少し高い待遇を条件に引き抜かれてしまった。

客層を広げ、美濃吉の知名度を高めたチェーンレストラン。父子の夢の一部がかなった瞬間。

他人資本を入れるリスクの大きさや、愛社精神を持つ人材の育成が難しいマニュアル経営の問題点を目のあたりにして、初めての挫折感を覚えた。それでも「お前の思うようにやったらええ」と任せてくれる父の後押しと、夢への変わらぬ情熱ですぐに体制を立て直し、翌年には全て自己資本で和食メニューも取り入れた「ジョイみのきち」を、京都の主要道路沿いに12店展開した。
マニュアル化で値段も手ごろに抑え、「初めて美濃吉で食事ができた」と喜ぶ家族連れなどが年間240万人も訪れた。その期待に応えようと「もっと美味しい和食を」とセントラルキッチンでの調理法や配送の工夫を重ねる日々。
しかし「満足した」という新規客の声とは裏腹に、美濃吉として納得できる味はなかなか出せない。古くからの常連客からも「なんでみのきっつあんはのれんを大事にせえへんのや」という声が上がる。「常連客だけで経営はやっていけん…」と聞き流しながらも、和食で全国展開を目指す難しさを感じた。
レストランチェーン開店から6年が過ぎ、38歳を迎えた1983年。10年前には一緒に夢を語り合った経営者たちの会社が、チェーン店化を成功させて上場をする一方で、美濃吉の出店はスタート時の12店舗のままストップしていた。