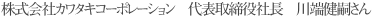
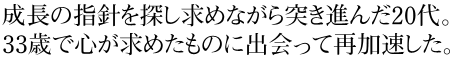


荒物店を開いた気性の激しい祖父と勝気な祖母、その跡を継いで荒物卸の仕事に没頭する猪突猛進型の父や、懸命に家族や社員の面倒を見る一途な母。個性ある大人たちに囲まれて、子ども心にいつも自分の芯になるものを探した。自ら硬派な立命館中を選んで進み、習字の時間には前の授業よりとにかく多く枚数を書き続けて3年間満点をもらうなど、いつも何かにのめり込んだ。
そんな中3のとき、それまで仕事のすべてを取り仕切っていた父が大病を患って生死をさまよい、入退院を繰り返し始めた。まるで別人のように弱ってしまった父を目の当たりにして、人間のはかなさを感じ、自分がシッカリしなければという思いも募り、政治や経済の世界の偉人たちの伝記を読み漁り始めた。
「人生って何や? 俺の使命は?」。そんな哲学を探すうちに政治家や弁護士に憧れ始め、高校では柔道に没頭して心身を鍛え、担任に指導を仰いで生徒会などでリーダーシップを学んだ。大学でもっと幅広い知識をつけ、別の世界で修行してから家業を継ごうと考えていた高3のある日、父から「大学ではなく家業に入れ」と言われた。自分の人生すら自由にできないことに愕然とした。
なんとか大学に進学しても年の半分は家業を手伝った。トラックを大学に乗り付け、授業が終わると配送に向かう日々。「主婦が使う台所用品を扱うのは俺には合わん」と感じながら、とにかくやるしかないと新規の荒物店に営業した。
誰からの教えもないまま仕事への取り組み姿勢を模索する。「ウチの得意先に営業するな!」と同業者から文句を言われ、「この閉鎖的な京都からいつか飛び出したい」と感じ、卒業を迎える頃には決して半端な気持ちでは入社したくない気持ちが高まった。自ら寺に3日間こもって座禅を組み、覚悟を決めた。

毎年10人前後の大学生を採用した。入社式でも自ら作った経営理念を語り始めた。

社長がいないときには朝礼でも机の上に座ったままの従業員もいる30人の会社。「会社なんやからもっと規律を大切に」と訴えると、取引先から「偉そうなことを言う前に実績を作らんと」と言われて、「必ずトップセールスマンになる」と猛烈に働いた。
既存の荒物店には固定の卸業者が入り込んでいたところが多かったので、小売業界の主役になっていたスーパーなどに営業し、カタログ販売というものを知るとすぐにその会社にも飛び込んで次々と取引先を増やして行く。日に何度も先方本部を訪問し、チラシ撮影用に30点の商品があれば良いところを60点持って行くなど、「バイヤーさんの期待に120%応えよう」と無心に働き続けると、比例するように取引も増えて行った。中でも生協の無店舗販売に強い魅力を感じた。
ただ、父からは「世話になった荒物店を大事にせんか!」と認めてもらえない。「もう小売業界は変わって行くんや」と訴えても、「お前は苦労を知らんから大切なことがわかってない」と強く言われた。それでも中四国や九州の生協などまで開拓して社内一の業績を上げ続け、仕入れも含めてすべてを仕切った。
26歳には過労と食事が原因になって出血性胃炎で緊急入院し、病室で「卸先の業態を絞らんと労力ばかりが増える…」と苦悩した。しかし同じ頃、物流センター兼用の立派な新社屋も完成して初の大卒生を採用すると、「彼らが誇りを感じる会社にしなければ」と更に規模拡大に突っ走る。「会社は社会の『公器』。経営者自ら公私混同せず、従業員の物心両面の幸せを約束することを根本に置く」と経営理念を作って自分に言い聞かせた。しかし、「俺にできることが何でできない!」という指導に、社員たちはなかなか心を寄せてくれなかった。

生協の無店舗販売は、スーパーなどへ卸すのとは違ってチラシの中でのPR方法次第で反響が変わり、自分が卸した商品の売れ行きがそのままわかるため、社員たちもヤリガイを感じていた。「卸先を絞るならこの業態だ」と、今度は東日本の生協に照準を合わせ、先頭に立って駆け回り、東北から関東の生協を開拓した。その一方で、それまで長年の間、会社の基盤を築かせてもらった荒物店を始めとする他の小売業態との取引を誠意で説得し続けて慎重に縮小して行った。
ただ、全国に納入先が増え、会社の席を温める間もなく自ら飛び回るうちに、従業員数が100人近くになった社内には問題が噴出した。父にも「お前のやり方に社員も離れて行くやないか」と理解してもらえず、29歳で結婚し、翌年に子どもが生まれても風呂に入れてやる心の余裕が持てない。たまの休日にも仕事のことが頭を離れず、過労が重なって熱を出して寝込むことがあっても、「経営って、リーダーって何や?」と、朦朧とする意識の中でもがき苦しんだ。
有名コンサルティング会社の指導員にアドバイスされても、著名な経営者の書物を読み、講話カセットを聞き漁っても納得できる指針は見つからない。「人より少し遅れても、遠回りしてでも、経営者としての信念を持ちたい…」。その飢えが頂点に達しようとしていた33歳のある日、破竹の勢いで成長する京セラの当時の稲盛和夫社長が経営塾を開くと知り、あらゆるツテを頼って入塾させてもらった。