
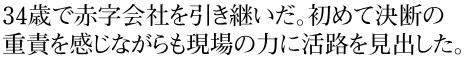


外国人に土産物を販売する商売を始めた祖父。その事業を大幅に拡大した父から「長男のお前が会社を守っていくんだぞ」と聞かされて、3歳にして周囲の大人に後を継ぐことを宣言した。広い自宅に月2~3回は従業員や工芸職人、旅行ガイド、業者など大勢を招いてよく語らっていた父と祖父。その様子を眺める傍らで、本社店舗によく遊びに行っては、外国人客や働く従業員の姿を見る日常を過ごした。
小4のとき、父が事業を進出させた東京に移り住むと、学級委員を務めて大勢を仕切る人気者になったのに、今度は父の方針で埼玉の全寮制の中高一貫校へ入学させられた。更に中3のときに、父に1年間のアメリカ留学を言いつけられても「会社を継ぐには英語が必要だ」と素直に受け入れ、日本語が一切通じない生活にも適応して「やればできる」と自信をつけた。13店舗までに店を増やして社長に就任した父は、「私が創業者のようなものだ」と自信に溢れ、母も「お父さんはすごいんだよ」とよく話していた。
高校時代は経営者が家族ぐるみで交流する会合でできた友人たちと気ままに遊ぶ一方、歴史小説を読んで偉大な父を持って苦しむ武田勝頼に共感したりもした。進学先としては、その友人たちの多くが行く慶應大ではなく、硬派なイメージで父の母校でもある早稲田大を選んだが、1浪後の受験にも失敗して初めて敗北感に打ちひしがれた。
1985年のプラザ合意を契機に急激な円高が続いた影響で、外国人観光客も突如減り始め、世間はバブル景気に踊り始めて活気づいていても、会社の売上は年々下がり続けた。そんな現状を打破しようと、父はカナダやハワイへの出店や、国内での開閉店を繰り返していた。仕事の手伝いを多少はしても、友人たちと海外旅行やパーティを楽しむ大学生でしかないのに、「家に来る社員たちは気楽そうだよ。もっと危機感を持たせなよ」と父に意見してみたりもした。ただ、ある酒席で一人の従業員から「社長は雇用を守るために出店までしてくれてありがたい」と聞いて、父の偉大さを垣間見る思いをした。

21歳のとき、旅行先に祖父の訃報が届いて、自宅に電話すると父が泣いていた。葬儀の後に、一時は売上を50億円にまで伸ばして自信に溢れていた父が、「迷ったときは、先代ならどう考えるかを頼りにしていたんだ…」とポツリと漏らす姿を黙って見ていた。
「まずは他の会社を見てみよう」と臨んだ就職活動。華やかな総合商社や銀行にも憧れながらも、「会社を継ぐときのために単価の小さな商品を扱う流通業に入ろう」と、父の口利きで海外にも多店舗展開するスーパーマーケットチェーン・ヤオハンに5年の約束で入社した。円高が更に進行して会社の売上がピーク時の半分近くにまでなっていた。「いつか俺がもう一度大きくするぞ」と、将来の自分をボンヤリ思い浮かべていた。
自ら現場を希望して静岡・御殿場店の精肉売場に配属された。待っていたのは肉の裁断やパック詰め、デッキブラシがけに包丁研ぎ、パート女性の愚痴を聞くばかりの毎日。ときに訪れる学生時代の友人に「よくこんな仕事やってるな」と言われ、客に怒鳴られる姿を両親に見られた。スーツ姿で颯爽と働く友人と比べて肉の臭いが体に染み付いた自分のカッコ悪さに、「何やってるんだ…」と虚しさが込み上げた。しかし、若き日の祖父や父も下働きした話を思い出して、「これも修行だ」と勤務時間を過ぎても頑張った。
ところが入社1年後、「経理を学べないなら帰ってこい」と焦る父の一言で、予定より4年も早く退職するハメになってしまった。しかも、住み慣れた東京ではなく京都勤務を命じられたのに、「もう働かせてもらえるんだ」と喜んで、課長という肩書きで入社した。円高は一層進んで売上も更に落ち込んでいて、店舗は5つにまで減っていた。


現場の従業員たちは温かく迎えてくれて、大きな本社店舗でまずは接客に精を出す毎日が始まった。ところが、女性ベテランスタッフは他の新人たちに対して、「10年早いわよ」などと得意客への対応や買付けなどの重要業務を任せない。その上、自分の売上実績を残すために高い買い物をする客にばかり厚遇して他の客からのクレームを招いていた。
しかし、現場の若手を育てるのが自分の役割。「現場を知らずして上には行けない。発言力のない自分は、休まず働いて実績を上げるしかない」と決意した。自ら従業員たちに話し掛け、周囲に「休め」と言われても月に3日も休まずに働き続けた2年間。するとやがて全販売員40人中2位の売上実績を残せて、周囲からも認められていった。
1995年、父は長年続く売上低迷の対策として、外国人向け事業のノウハウが一切通じない日本人観光客をターゲットにした事業を本格的に始め、その店舗となるビルを新築することになった。数年前から始まっていたバブル崩壊の影響で金融機関の経営破たんが相次ぐなか、貸し渋りを乗り越えて資金を調達してきた父。26歳で取締役営業部長に就任して、本社店舗横に日に日に仕上がっていく建設中のビルを間近で見つめながら、「父はこの決断で従業員の雇用を守ろうとしているんだ」と、尊敬の念が高まった。
外国人向け事業の営業責任者として、今度は京都だけに留まらず全店舗に出向いて現場に目を配る日々。そんななか、もうわからないはずの現場に口出ししてくる父。「財務関係の仕事はまだ何もできないけど、2年間汗水たらしてきた俺が現場を一番わかっているんだ…」。そんな想いで人事異動に反対したり、面接の体制を少人数制に切り替えて、ミスマッチのない採用へ向けて応募者一人ひとりとジックリ対話するようになった。
個人単位に設定されていた目標をチーム単位に変更してみると、やはりうまく回らなくて父の考えの深さを痛感もしたが、「企業にとって人が何より大切だ」との想いは高まっていった。現場の話以外でも、「そのやり方で本当に合ってる?」と、あえて父に異を唱え続けた。